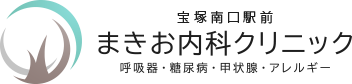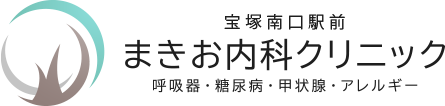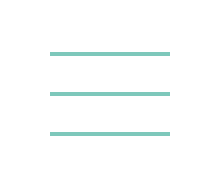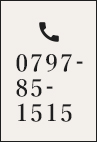息切れ・横になると息苦しい
(息切れ)とは
 息切れや横になった際の息苦しさ、呼吸困難などは、体が「酸素不足ですよ」とサインを送っている生理的な現象です。
息切れや横になった際の息苦しさ、呼吸困難などは、体が「酸素不足ですよ」とサインを送っている生理的な現象です。
これらの呼吸に関する症状は、心疾患などでみられるため、重い病気のサインとして発生している可能性があり、注意が必要です。また、原因が複数併存していることもよくあるため、総合的な判断が必要です。
「坂道や階段を上る時に息切れを起こす」「平地を今まで通りの速度で歩行しても息切れになる」「呼吸が荒くる」「浅く速い呼吸の繰り返し」「深呼吸しないと息苦しくなる」などの症状がみられる場合は、速やかに医療機関への相談をお勧めします。
横になると息苦しい
(息切れ)の原因
気管支喘息
気管支喘息があると、自律神経の働きによって睡眠中に呼吸が苦しくなることがあります。
特に、早朝に症状が現れやすい傾向にあります。この息苦しさは、気管支の慢性的な炎症により、気管支が腫れ上がり、気道が狭まるために生じます。気道が狭まると、喘鳴と呼ばれる「ヒューヒュー」「ゼーゼー」という音を伴う呼吸困難が起こります。
以下のような状況になると、息苦しさが発生しやすくなります。
息苦しくなるタイミング
- 夜間から明け方にかけて
- 季節の変わり目
- 疲れが蓄積している時
- 天候が荒れ模様の日
- 風邪を引いた際
- タバコの煙や香りの強い線香、
刺激的な匂いをかいだ時 - 気管支喘息の発作
慢性閉そく性肺疾患
 慢性閉そく性肺疾患(COPD)は、長期的な喫煙により肺に持続的な炎症が生じる病態です。
慢性閉そく性肺疾患(COPD)は、長期的な喫煙により肺に持続的な炎症が生じる病態です。
この疾患の典型的な症状には、頻繁な咳、体を動かした時の呼吸困難があり、これらは時間と共に徐々に悪化していきます。
また、横になると痰が絡み、息苦しさも起こりやすくなります。さらに、以下の症状もみられることがあります。
症状
- 頻繁に咳が出る
- 喘鳴があり、呼吸時に「ゼーゼー」
「ヒューヒュー」という音がする - 皮膚が紫色~黒色に変色する、
チアノーゼがみられる - 体重が減る
- 胸部がビール樽のように見えるほどに膨らむ
- 指先が太鼓のバチのように腫れる
心不全
心不全は、心臓の血液を全身に送る機能が衰えてしまう状態です。横になった際に息苦しさを感じる場合、心不全を発症している可能性があるため、放置は禁物です。
心不全が進むと、腎臓への血液の流れが阻害され、水分の排出が困難になります。
これにより、体がむくむ、または肺周囲に液体が溜まるようになります。肺に液体が溜まると、呼吸しても酸素が十分に取り込めず、息苦しさが生じます。この息苦しさですが、睡眠に支障をきたすほどになることもあります。
症状
- 息切れ
- 動悸
- 呼吸困難
- むくみ
副鼻腔炎
 副鼻腔炎は、風邪の原因となる細菌やウイルス、そしてアレルギー反応などにより副鼻腔の粘膜に炎症が生じる状態で、粘り気のある鼻水が特徴です。この鼻水が喉に流れ込むことで炎症が生じ、咳が増えて呼吸が苦しくなることがあります。さらに、以下のような症状が出ることもあります。
副鼻腔炎は、風邪の原因となる細菌やウイルス、そしてアレルギー反応などにより副鼻腔の粘膜に炎症が生じる状態で、粘り気のある鼻水が特徴です。この鼻水が喉に流れ込むことで炎症が生じ、咳が増えて呼吸が苦しくなることがあります。さらに、以下のような症状が出ることもあります。
症状
- 鼻詰まり
- 鼻水
- 喉に鼻水が流れる
- 嗅覚障害
- 咳が出る
- 頭痛
- 顔面が痛くなる
- 倦怠感
- 発熱
- 口臭
睡眠時無呼吸症候群
睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に呼吸が一時的に停止することを繰り返し、その結果、睡眠の質が損なわれる病気です。
発症する原因は多岐にわたりますが、睡眠中に舌が後ろに落ち込むことで気道が狭まり、酸素の確保が困難になることが一因です。気道が狭まると酸素が不足し、呼吸が不規則になり、息苦しさを感じるようになります。さらに、夜間の酸素不足は睡眠の質を下げ、日中の過度な眠気の原因となります。
症状
- いびきが出る
- 夜中に起きてしまう
- 不眠
- 昼間の強い眠気
- 不整脈
- 呼吸障害
自律神経失調症
 自律神経失調症は、体の機能を取り仕切る自律神経である交感神経と副交感神経のバランスが乱れてしまう状態です。
自律神経失調症は、体の機能を取り仕切る自律神経である交感神経と副交感神経のバランスが乱れてしまう状態です。
発症すると、呼吸が浅くなったり速くなったりし、息苦しさを感じることがあります。「呼吸がおかしい」と感じた際には、意識して深呼吸を行うと良いでしょう。
自律神経失調症に陥ると、身体機能の調節が難しくなり、様々な症状が起こるようになります。
症状
- めまい
- 食欲不振
- 耳鳴り
- 吐き気
- 動悸
- 便秘や下痢
- 腹痛
パニック障害
パニック障害は、身体的な異常がないにもかかわらず、予期せぬ動悸、呼吸困難、めまいなどの発作が反復して起こる精神疾患です。発作時には、激しい不安や恐れが伴います。
発症原因は完全には解明されていませんが、日々のストレスが積み重なっている方に発症することが多いです。主な症状は以下の通りです。
症状
- めまいがする
- 頭がふらふらする
- 物事に対して現実感がない
- 発作が何度も起こる
- 「発作が起きたらどうしよう」と予期不安を起こす
- うつ病や不安障害を引き起こすリスクがある
横になると息苦しい
(息切れ)の検査
 横になると息苦しさを感じる場合、心臓や呼吸器系の疾患が潜んでいる可能性があるため、早急に医療機関を受診することが重要です。
横になると息苦しさを感じる場合、心臓や呼吸器系の疾患が潜んでいる可能性があるため、早急に医療機関を受診することが重要です。
診断には、問診や血液検査のほか、心電図、胸部X線、呼気NO検査、呼吸機能検査が行われ、パルスオキシメーターを用いて血中酸素濃度が測定されます。
これらの基本検査に加えて、CTスキャン、血管造影、換気血流シンチグラフィーなどの追加検査が必要と判断された場合は、専門の医療施設をご案内します。
横になると息苦しい
(息切れ)の治療
 初めに行うのは、検査によって息切れの原因となる疾患を明らかにすることです。
初めに行うのは、検査によって息切れの原因となる疾患を明らかにすることです。
心不全、弁膜症、冠動脈疾患、不整脈などが息切れの原因である場合、それぞれの病状に応じた治療が施されます。
治療の基本は、食生活の見直しや運動療法、薬物療法などで、状況に応じて心臓カテーテル手術やカテーテルアブレーション、ペースメーカーの埋め込み手術なども考慮され、必要であれば専門医療機関への紹介も行います。
特に、心不全によって息切れが起きている場合は、肺や全身に余分な水分が溜まっているため、水分や塩分の摂取を制限します。