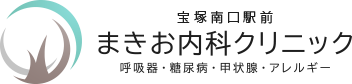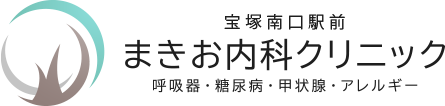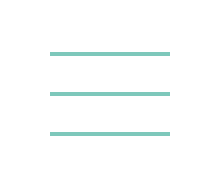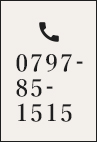当院の呼吸器内科の強み
呼吸器内科専門医による
呼吸器・アレルギーの専門的な治療
 当院では日本呼吸器学会認定の呼吸器専門医が上気道炎、気管支炎、肺炎、肺結核、気管支喘息、COPD(慢性閉塞性肺疾患)、肺がん、間質性肺炎などの呼吸器疾患に対して、幅広い診療に提供しています。
当院では日本呼吸器学会認定の呼吸器専門医が上気道炎、気管支炎、肺炎、肺結核、気管支喘息、COPD(慢性閉塞性肺疾患)、肺がん、間質性肺炎などの呼吸器疾患に対して、幅広い診療に提供しています。
また、アレルギーでお悩みの患者さまに対して患者さまが反応する特定の物質を明らかにし、環境調整のアドバイスやアレルギー治療薬の処方を行っています。
咳喘息・気管支喘息・小児喘息の
診断と治療
肺機能検査(スパイロメトリー)

呼気NO検査(気道の炎症を可視化)

「咳が長引く」「夜間や朝方に咳き込む」「季節の変わり目に息苦しさがある」などの症状は、風邪やアレルギーではなく咳喘息や気管支喘息が原因の可能性があります。当院では、呼吸器専門医が最新の検査機器を活用し、咳の原因を的確に診断します。
咳喘息は放置すると、気管支喘息へ進行するリスクもあります。特に小児喘息は成長と共に変化するため、年齢や体格に応じたきめ細やかな管理と治療が重要です。
当院では、
- 肺機能検査(スパイロメトリー)
- 呼気NO検査(気道の炎症を可視化)
- アレルギー検査(IgE、皮膚テストなど)
を組み合わせて原因に基づいた診療を行い、吸入ステロイドや抗アレルギー薬、環境改善アドバイスなどを通じて、一人ひとりに合わせた治療方針をご提案します。
「ただの咳」と思わず、呼吸器の専門家にご相談ください。早期発見・早期治療が症状の改善と生活の質向上につながります。
いびき・睡眠時無呼吸症候群(SAS)の精密検査と治療
「いびきがうるさいと指摘された」「朝起きても疲れが取れない」「日中に強い眠気がある」そんな症状は、睡眠時無呼吸症候群(SAS)のサインかもしれません。
睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に呼吸が何度も止まる病気で、放置すると高血圧・心筋梗塞・脳卒中・糖尿病などの生活習慣病リスクが高まることが分かっています。
当院では、
- 自宅でできる簡易睡眠検査
- 終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG)
を通じて、睡眠時無呼吸症候群の有無と重症度を正確に評価します。
軽度の方には生活習慣の見直しやマウスピース療法、中等度以上の方にはCPAP(持続陽圧呼吸)療法を提案し、定期的なフォローも丁寧に行います。
特に肥満傾向の方・高血圧・糖尿病のある方はリスクが高いため、早めの受診が肝心です。「いびきは体質だから…」と諦めず、質の高い睡眠と健康を取り戻す第一歩を、当院で踏み出しましょう。
アレルギー性鼻炎・花粉症の
根本治療「舌下免疫療法」に対応
毎年のように花粉症に悩まされている方、薬を飲んでも効果が薄いと感じている方には、舌下免疫療法という新たな選択肢があります。
舌下免疫療法とは、アレルゲン(スギ花粉やダニ)を少量ずつ体内に取り込み、免疫反応を穏やかにしていく根本治療です。症状の緩和だけでなく、長期的には薬の使用量や頻度を減らすことが期待されます。
当院では、
- スギ花粉症、ダニアレルギー(通年性鼻炎)に対応
- 治療の適応判断のための事前アレルギー検査を実施
医師の管理のもと、自宅で毎日舌下に薬剤を投与するだけなので、忙しい方でも続けやすい治療法です。副作用や治療期間、費用なども丁寧にご説明します。
花粉症の時期だけでなく、症状が落ち着いている時期の開始が理想的です。
呼吸器内科について
 呼吸を通じて取り込まれた空気は、鼻や口を通り、気管や気管支を経て肺に到達します。鼻から喉にかけての通り道を上気道、気管から肺までの通り道を下気道と称します。
呼吸を通じて取り込まれた空気は、鼻や口を通り、気管や気管支を経て肺に到達します。鼻から喉にかけての通り道を上気道、気管から肺までの通り道を下気道と称します。
呼吸器系の一般的な疾患には、風邪、扁桃炎、咽頭炎などの上気道炎、気管支炎、肺炎、肺結核、気管支喘息、COPD(慢性閉塞性肺疾患)、肺がん、間質性肺炎などが含まれます。これらの多岐にわたる呼吸器疾患に対して、当院では日本呼吸器学会認定の呼吸器専門医が広範囲にわたる診療を提供しています。
よくある疾患
- 慢性咳嗽(がいそう)
- 気管支喘息
- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
- 睡眠時無呼吸症候群
よくある症状
- 慢性的な咳があって治らない
- 痰が絡む
- 頻繁に息切れが発生する
- 風邪を引きやすく、回復も遅い
- 咳によって睡眠が妨げられる
- 呼吸時に「ゼーゼー」「ヒューヒュー」
といった異音がする - 過去に喘息と診断された経験がある
- ご家族の中に喘息患者がいる
- 元々アレルギー体質でいる
慢性咳嗽・長引く咳
 咳嗽(がいそう:一般的には咳と言います)とは、肺や気管支に入った異物を体外に排出するための自然な防御反応です。しかし、咳が長引くと生活の質が低下し、日常生活や仕事に支障をきたすことがあります。
咳嗽(がいそう:一般的には咳と言います)とは、肺や気管支に入った異物を体外に排出するための自然な防御反応です。しかし、咳が長引くと生活の質が低下し、日常生活や仕事に支障をきたすことがあります。
咳の種類は、3週間以内に治る「急性咳嗽」、3週間~8週間続く「遷延性(せんえんせい)咳嗽」、8週間以上も長引く「慢性咳嗽」に分けられます。
咳の原因には感染症、アレルギー、異物の侵入、悪性腫瘍、胃酸逆流(逆流性食道炎)、咽喉の異常、ストレスなどがあります。当院では、これらの原因を特定し、適切な治療を行います。
気管支喘息
 気管支喘息は、気管支に慢性的な炎症が生じることで、空気の流れが制限されて呼吸がしづらくなる病気です。わずかな刺激で気管支壁が反応し、腫れや筋肉の収縮により咳や喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒューという音)が生じ、時には痰も伴います。乾燥した季節、ハウスダスト、タバコの煙、風邪の原因となるウイルス、ストレスなどが症状を悪化させる要因となります。当院では、日本呼吸器学会認定の呼吸器専門医が気管支喘息の治療を行なっています。長引く咳、痰の絡み、息苦しさなどの症状でお困りの方は、症状が悪化する前にお気軽にご相談ください。
気管支喘息は、気管支に慢性的な炎症が生じることで、空気の流れが制限されて呼吸がしづらくなる病気です。わずかな刺激で気管支壁が反応し、腫れや筋肉の収縮により咳や喘鳴(ゼーゼー、ヒューヒューという音)が生じ、時には痰も伴います。乾燥した季節、ハウスダスト、タバコの煙、風邪の原因となるウイルス、ストレスなどが症状を悪化させる要因となります。当院では、日本呼吸器学会認定の呼吸器専門医が気管支喘息の治療を行なっています。長引く咳、痰の絡み、息苦しさなどの症状でお困りの方は、症状が悪化する前にお気軽にご相談ください。
慢性閉塞性肺疾患(COPD)
慢性閉塞性肺疾患(COPD:Chronic Obstructive Pulmonary Disease)は、かつて「慢性気管支炎」や「肺気腫」と称された病気群を指します。環境汚染物質やタバコの煙など、有害な物質の吸入により気管支や肺に炎症が生じ、空気の流れが制限され、呼吸機能が低下します。世界で死因の第3位を占めるこの疾患は、日本では喫煙者に多くみられ、「肺の生活習慣病」とも呼ばれています。COPDは単に肺だけでなく、様々な併存疾患を伴うことから、“全身性疾患”としても捉えられてきています。
初期には自覚症状がほとんどありませんが、気管支が慢性的に炎症を起こし、肺胞(空気中の酸素を血液中に取り込む器官)が破壊されて機能が落ちてくると、呼吸困難感や意欲低下、身体活動性の低下へつながり、全身の機能低下に陥ります。さらに進行すると、酸素の取り込みや二酸化炭素の排出が困難になります。治療には禁煙が最優先であり、気管支拡張薬の吸入が基本となり、場合によってはステロイド薬も使用します。呼吸器リハビリテーションを含む理学療法も併用されることがあります。また、肺機能の低下を考慮して、インフルエンザや肺炎球菌のワクチン接種も必要になります。
肺炎
 肺炎は、細菌やウイルスによる「感染性肺炎」と、アレルギーや薬剤反応、自己免疫反応などによる「非感染性肺炎」に大別されます。
肺炎は、細菌やウイルスによる「感染性肺炎」と、アレルギーや薬剤反応、自己免疫反応などによる「非感染性肺炎」に大別されます。
感染性肺炎は全年齢層で見られ、高齢者においては主要な死因となっています。
風邪と似た症状が現れるものの、1週間以上続く強い咳や痰があれば感染性肺炎を疑われます。通常、体内の免疫機能が異物を排除しますが、この機能が低下すると肺炎にかかりやすくなります。若年層でも発症することはありますが、特に免疫力が低下している高齢者は注意が必要です。
治療法は感染した病原体に応じて異なり、細菌感染の場合は抗菌薬で治療し、ウイルス感染の場合は抗炎症薬や解熱鎮痛薬、去痰薬、鎮咳薬などの対症療法が主に実施されます。
気管支炎
気管支炎は、感染による「急性気管支炎」と、アレルギーや喫煙などが原因の「慢性気管支炎」に大別されます。慢性気管支炎は、慢性閉塞性肺疾患(COPD)の一形態です。
急性気管支炎は主に細菌やウイルスによる感染が原因であり、細菌感染の場合は特定の抗菌薬が処方されますが、ウイルス感染では鎮痛解熱薬や消炎鎮痛薬、鎮咳薬、去痰薬などの対症療法が用いられ、咳や痰、発熱などの症状を緩和します。
睡眠時無呼吸症候群
 睡眠時無呼吸症候群(SAS:Sleep Apnea Syndrome)は、睡眠中に呼吸が一時的に停止する病気です。睡眠中に10秒以上の無呼吸が1時間に5回以上生じる場合、「睡眠時無呼吸症候群」と診断されます。1時間に20回以上の無呼吸が確認される場合は「中等症」とされます。
睡眠時無呼吸症候群(SAS:Sleep Apnea Syndrome)は、睡眠中に呼吸が一時的に停止する病気です。睡眠中に10秒以上の無呼吸が1時間に5回以上生じる場合、「睡眠時無呼吸症候群」と診断されます。1時間に20回以上の無呼吸が確認される場合は「中等症」とされます。
無呼吸による低酸素状態は、身体が酸素を求めて無意識に覚醒を促します。このため、睡眠が断続的になり、慢性的な睡眠不足を引き起こします。これが原因で、日中の強い眠気、集中力・判断力の低下、交通事故など、日常生活に様々な悪影響を引き起こします。
ほとんどの場合、生活習慣病が原因とされますが、ストレスなどの心理的要因も睡眠時無呼吸症候群を引き起こしやすくします。
さらに睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中の低酸素や日中の眠気によるストレスが高血圧や脳卒中、心筋梗塞などの虚血性心疾患のリスクを高め、糖尿病や脂質異常症といった合併症を引き起こし、場合によっては突然死に至ることもあります。
「いびきがひどいと言われる」「家族から無呼吸を指摘された」「寝ても疲れが取れず、すごく眠い」などのお悩みを抱える方は、お気軽にご相談ください。