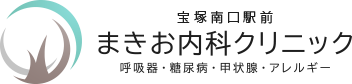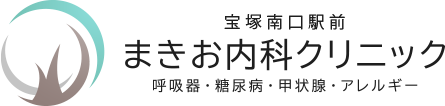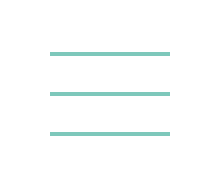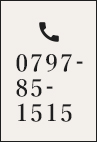食べ過ぎ・飲み過ぎが気になる年末年始に
みなさまこんにちは。副院長の牧尾登紀です。
2025年も残すところわずかとなりました。今日は糖尿病患者さんへ向けて、年末年始の過ごし方について少しお話させていただこうと思います。
年末年始は、クリスマス、忘年会、お正月と楽しいイベントが多く、血糖値の管理が難しくなりやすい時期です。毎年1月、2月はHbA1cが上がるという方も少なくないと思います。これからやってくる年末年始を上手に乗り切るために、ちょっとした工夫をお伝えします。
①食べる量を決める
クリスマスにはケーキ、お正月にはおせち料理やお餅を楽しみにされている方も多いと思います。糖尿病だから食べてはいけないということはありません。大切なのは、食べる量を決めることです。小皿に1食分を取り分けて量を確認しながら食べるようにしましょう。
おせち料理は日持ちをさせるために、塩・砂糖・みりんなどが多く使われているため、食べ過ぎには注意が必要です。
お餅は、切り餅2個(100g)が白米150g相当の糖質量となりますので、切り餅2個をご飯1杯分に置き換えて食べるようにしましょう。あんこやきな粉の付け過ぎには注意です。
②飲酒は適量を守る
糖尿病患者さんも適量であれば飲酒は可能です。むしろ適度な飲酒は、ストレス解消やリラックス効果に繋がります。
厚生労働省の指針では、1日の摂取アルコール目安量を20g程度としています。実際のアルコール飲料で換算すると、ビール中瓶1本(500ml)、日本酒1号(180ml)、焼酎0.6号(100ml)、ワイングラス2杯(180ml)となります。
注意点としては、食事を取らずに飲酒をすると低血糖になる恐れがあるので、食事と一緒に飲酒するようにしましょう。また、利尿作用がありますので水も一緒に飲むようにしましょう。
③体重を毎日測る
多くの方がこの時期に1.5kg以上体重が増えるといわれています。食べすぎた翌日は体重計に乗るのをためらいがちですが、増えた体重を見ることで次の食事量を意識することができます。毎日同じ条件で測り、年末年始の体重増加に気をつけましょう。
偉そうに注意点をお話させていただきましたが、私も毎年正月は体重が増えるので気を付けて過ごしたいと思います・・・。